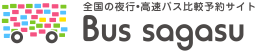全八幡宮の総本宮である大分県宇佐市「宇佐神宮」に参拝しよう

日本全国に約4万社あるとされる八幡宮ですが、ここ大分県宇佐市にある宇佐神宮が総本宮です。宇佐神宮は欽明天皇32年に、応神天皇の御神霊が八幡大神として現れたことが起源とされています。
神武天皇の顕彰碑を始め、国宝に指定されている本殿もある宇佐神宮はたくさんの見所があります。
今回はこちらをご紹介します。
Index
宇佐駅は既に境内のよう?

宇佐駅に降りると、既に御神燈が下げられており、神社の境内に入ったような気持ちになります。ここからはバスやタクシーを使って宇佐神宮まで行くのが一般的です。バスは早朝、また夕方も時間が遅くなると本数が減り不便になりますので、事前に調べておきましょう。
少し時間はかかりますが、神宮までは5キロ程ですから、歩いて行くことも出来ます。途中では史跡の船つなぎ石があり、見学することが出来ます。歩いて行くのもまた楽しいのではないのでしょうか。
広い境内

凛とした雰囲気の宇佐神宮では、気持ちがピリリと引き締まる感じがします。国指定史跡部分だけでも約25ヘクタール、全体では60ヘクタールにもなり、かなりの広さです。
神武天皇顕彰碑

宇佐神宮参拝の前に見ておきたい場所があります。それが黒男神社の手前にある神武天皇の顕彰碑なのです。駐車場に近い側にありますので、見落とさないようにしましょう。
日本書紀には、神武天皇東征の際、日向を出発して豊後水道を抜け、宇佐に上陸したとあります。この顕彰碑は昭和15年と比較的新しいものですが、神武天皇の上陸を記念して建てられました。
神橋

寄藻川にかかる神橋です。このように橋の先が見えないようになっています。この先は神域であることを意味しているのです。
黒男神社

黒男神社の御祭神は武内宿禰です。第12代から16代までの5天皇に240年余り仕えたという伝説の忠臣です。長寿、忠誠、奉仕の神として崇められています。大鳥居の外にあり、大神を護る役割があるとされます。なお、日本書紀では「武内宿禰」、古事記では「建内宿禰」となっています。
西大門

手水舎から表参道を約8分で上宮に至ることが出来ます。若宮神社を過ぎて上宮の手前に西大門があります。文禄(1592年 – 1596年)頃の建造とされています。安土桃山時代の様式であることから全体からみれば少し変わった形にも見えます。
上宮

上宮の手前は県指定重要文化財である見事な朱色の勅使門(南中楼門)です。ここを見るだけでも圧倒的な力を感じられそうです。
正面5.34m、側面3.17m、背は10.6mとなっており、こちらには御門の神として高良大明神、阿蘇大明神が祀られています。
上宮の本殿は国宝となっており、御祭神は三体の神様で、八幡大神は応神天皇と同一視されています。そして比売大神、神功皇后です。
八幡大神の一之殿は神亀2年(725年)建立とされています。比売大神の二之殿は天平元年(729年)、そして神功皇后の三之殿は弘仁14年(823年)に建立され、現在の形式の本殿が完成したとされています。
二拝四拍手一拝と通常の神社とは異なる作法となっていますので、参拝の際は注意が必要です。
百段を下る

南大門方向に石段を下り、右に進んでいくと、下宮が見えてきます。この通りは特に自然が多く、朱色の欄干とのコントラストは見事なものです。とても雰囲気の良いところですのでぜひ通ってみて下さい。
下宮

「下宮参らにゃ片参り」と言われ、上宮、下宮のどちらもお参りするのが良いこととされています。上宮だけで終わらないようにしましょう。
下宮は嵯峨天皇の弘仁年間(810年代)に勅願によって創建されました。上宮と同じ祭神が祀られています。上宮同様に皇室の方々も下宮へご参拝されるのです。
古くは御炊殿と呼ばれており、神前に供える食事用の竈があった場所とされています。また、農業、漁業の発展の神として崇められ、国民一般の祈願が行われてきたのです。
最後に
いかがでしたか?日本全国にある八幡宮の総本宮である「宇佐神宮」は長い歴史を持ち、国宝をはじめとした多くの建築物は見事です。
境内の凛とした雰囲気と、多くの自然があるこの地に参拝し、パワーをもらって下さい。
2016年1月15日